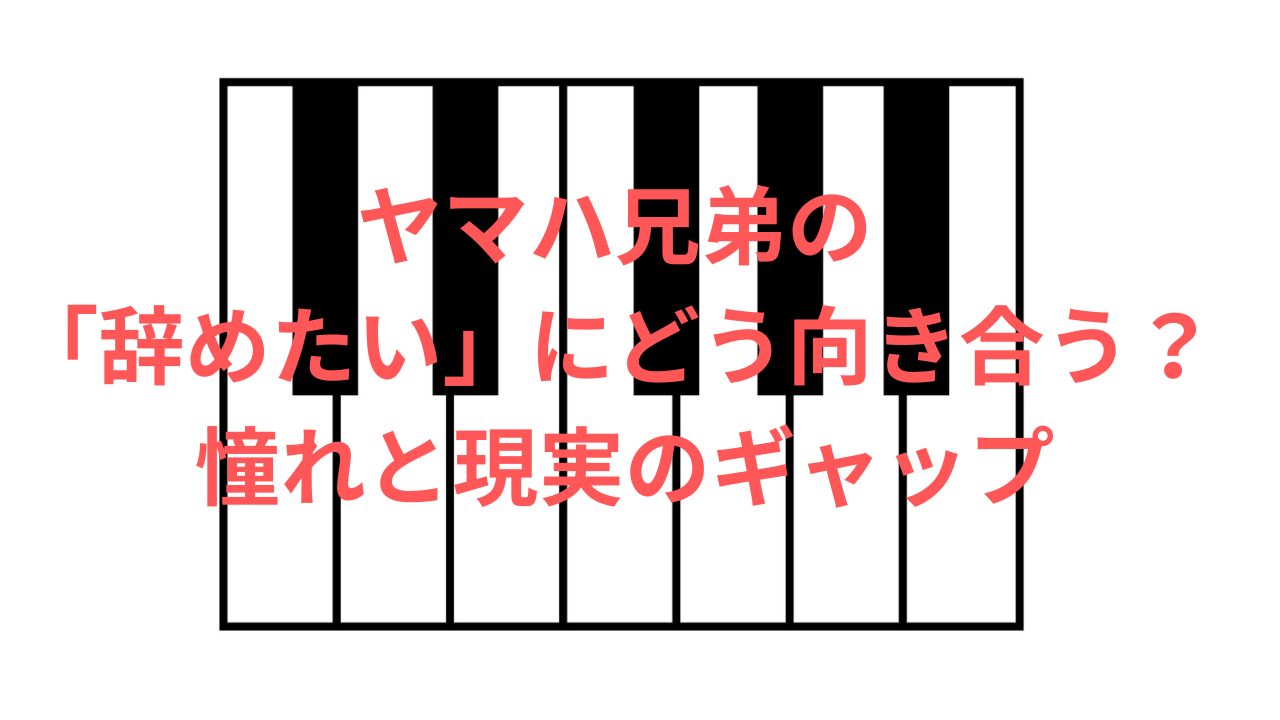ヤマハ音楽教室に通うごきょうだい、ジュニア科でコツコツ頑張るお兄さま(お姉さま)と、ぷらいまりーで「辞めたい」と格闘中の5歳の下のお子さま。お兄さま(お姉さま)の姿に憧れて「自分もヤマハに通う!」と意気揚々と始めたピアノ。上のお子さまのレッスンに一緒に参加しておられたので、初めは「よくできる子」だっただけに、両手奏の壁は大きな試練ですね。下のお子さまはお調子者でマネっこ好きな性格も、今の状況に影響しているのかもしれません。上のお子さまは器用でなくともコツコツするタイプでジュニア科の今では毎日練習する習慣がついていて、下のお子さまも同じようにほぼ毎日練習するのですが、弾けないとすぐ「辞めたい」の一言。親御さんは、いつか二人で楽しそうに連弾する姿を夢見ているそうで、下のお子さまの「辞めたい」発言は悩ましいことですね。
今回は、下のお子さまの「辞めたい」気持ちに寄り添いながら、その個性と才能を伸ばし、ごきょうだいで音楽を楽しむ未来へとつなげるための具体的なヒントを私なりに考えてみました。
1. 「辞めたい」の裏にある、お調子者さんの繊細な心
まず、下のお子さまの「辞めたい」という言葉の裏にある心理を、その性格と照らし合わせながら探ってみましょう。
- 憧れが強いゆえのギャップ: お兄さま(お姉さま)のレッスンを見て「自分もすぐに、あんな風にできる!」と、高い理想と期待を持っていたはずです。マネっこが得意な分、イメージ通りにいかない現実とのギャップに、人一倍戸惑いや「こんなはずじゃなかった」という気持ちを抱きやすいのかもしれません。
- 「できる自分」でいたいプライド: 「よくできる子」と見られていた経験は、お調子者タイプのお子さまにとって大きな自信の源です。両手奏でつまずき、他のお子さんがスムーズに弾いている(ように見える)状況は、そのプライドを揺るがし、「できない自分を見せたくない」という気持ちから「辞めたい」という言葉につながっている可能性があります。
- 注目されたい気持ちの裏返し: お調子者さんは、注目されたり褒められたりするのが大好き。うまく弾けていた時はたくさんの注目を浴びていたのに、今はできないことで注目されてしまう(あるいは注目されなくなる)と感じているのかもしれません。「辞めたい」と言うことで、親御さんの気を引きたい、もっと自分に関心を持ってほしいというサインの可能性も。
- フラストレーションの表現: 単純に、思い通りに弾けないことへのイライラや悔しさを、一番手っ取り早い「辞めたい」という言葉で表現しているとも考えられます。
2. きょうだいそれぞれの個性を尊重し、伸ばす関わり方
お二人の異なるタイプですよね。それぞれの個性を理解し、それに合わせた関わり方を心がけることが大切です。
- 上の子(コツコツ派)さんへ:
- 努力が実を結ぶ喜びを知っているお子さまは、下のお子さまにとって素晴らしいロールモデルです。その頑張りを認め、褒めてあげましょう。
- ただし、下のお子さまへの声かけで「お兄ちゃん(お姉ちゃん)はちゃんとやってるのに」といった比較は禁物です。
- 下の子(お調子者・マネっこタイプ)さんへ:
- 褒め方を工夫する:
- 具体的に、少し大げさに: 「わぁ!今の指の形、すごくキレイだったよ!天才じゃない?」「この前よりスムーズに弾けたね!さすが〇〇ちゃん!」など、お調子者な部分をくすぐるような、感情豊かな褒め方が効果的です。
- 「できた!」瞬間を逃さない: 小さなことでも「できた!」瞬間にすかさず褒めることで、達成感を強く印象づけます。
- マネっこをポジティブに活かす:
- 「お兄ちゃん(お姉ちゃん)が弾いてるあの曲の、この部分だけマネして弾いてみようか?」と、憧れの対象に近づけるような声かけを。
- お母さまやお父さまが楽しそうにリズムを叩いたり、口ずさんだりするのをマネさせるのも良いでしょう。
- 短時間集中、変化をつけて飽きさせない: 練習時間は短く区切り、「次は〇〇ゲームをしながら練習しよう!」など、遊びの要素や変化を取り入れると集中力が持続しやすくなります。
- 褒め方を工夫する:
3. 「辞めたい」を乗り越える!家庭での練習サポート術
毎日の練習習慣は宝物。それを活かし、下のお子さまの「辞めたい」気持ちを上手に乗りこなし、自信へと繋げるための具体的なアイデアです。
- まずは共感、そして理由を聞く:
- 「辞めたいくらい、今日の練習は難しかったんだね」「そっか、〇〇ちゃんは今、そんな気持ちなんだね」と、まずはお子様の言葉と感情をそのまま受け止めましょう。
- 「どうしてそう思うの?」「どの部分が一番イヤだと感じる?」と、優しく尋ね、話せる範囲で気持ちを表現させてあげましょう。
- 「他人とではなく、過去の自分と比べる」を徹底:
- 特にきょうだい間での比較は絶対に避けましょう。
- 「昨日より、ここの音がしっかり出せるようになったね!」「1週間前はここまで弾けなかったのに、すごい進歩だよ!」と、本人の成長に焦点を当てます。
- スモールステップと「劇場型」成功体験:
- 目標は小さく、具体的に: 「今日はこの1小節だけ、ゆっくり完璧に弾けるようにしよう!」「この曲の最初のフレーズだけ、お兄ちゃん(お姉ちゃん)みたいにかっこよく弾いてみよう!」など。
- 「できた!」を家族で盛大に祝う: 小さな目標でも達成したら、「やったー!すごい!パパ(ママ)にも聞かせよう!」と家族みんなで喜びを分かち合い、達成感を演出します。お調子者タイプのお子様は、こうした「発表の場」や「賞賛」が大好きです。
- 練習を「遊び」に変える工夫:
- ゲーム感覚で: 「サイコロを振って出た数だけ弾く」「ストップウォッチでタイムを計って、昨日より速く弾けるかな?」など、ゲーム要素を取り入れます。
- ご褒美シールやスタンプラリー: 目標達成ごとにシールを貼るなど、目に見える形で頑張りを可視化するのも効果的です。
- 「なりきり」練習: 「今日は有名なピアニストさんになりきって弾いてみよう!」など、想像力を刺激する声かけも。
- 「辞めたい」と言った時の魔法の言葉(お調子者タイプ向け):
- 夢をチラつかせる: 「えーっ、辞めちゃうの?〇〇ちゃんがピアノ上手になったら、お兄ちゃん(お姉ちゃん)と二人で連弾できるのになぁ。あの素敵な曲、一緒に弾けたら最高なのに、もったいない!」
- ちょっとしたご褒美作戦: 「そっかぁ。でも、この難しいところだけクリアできたら、今日は特別にアイス食べちゃおうか?」
- ユーモアで切り返す: 「大丈夫、大丈夫!ママ(パパ)が応援パワーを送るから、もう一回だけチャレンジしてみよう!えいっ!(と魔法をかけるフリ)」
- 上の子の存在を「憧れ」の対象としてキープ:
- 「お兄ちゃん(お姉ちゃん)も、小さい頃はこの曲で苦労したんだよ。でも、毎日ちょっとずつ練習して弾けるようになったんだって。どうやって練習したか、後で聞いてみようか?」
- 下のお子さまが素直に聞ける関係であれば、お兄さま(お姉さま)に「ここ、どうやって弾いたらいいか、ちょっとお手本見せてあげてくれる?」と先生役をお願いしてみるのも良いでしょう。
- 二人でいる時に、「いつか二人でこの曲を連弾したら、お客さん(じいじやばあばなど)もびっくりするだろうね!楽しみだなぁ」と、親御さんの夢を語りかけ、ワクワク感を共有します。
4. 親御さんの夢「二人で連弾」をモチベーションに!
「二人で連弾」という夢は、下のお子さまにとっても大きなモチベーションになり得ます。
- 簡単な連弾曲に触れさせる: 先生に相談し、ぷらいまりーのお子さまでも楽しめるような、ごく簡単な連弾曲やアンサンブル楽譜がないか聞いてみましょう。片手だけでも参加できるようなものでも良いです。
- 「なんちゃって連弾」体験: 上のお子さまが弾いている曲の、本当に簡単な一部分(例えば、同じ音をリズムに合わせて弾くだけでも)を下のお子さまが担当し、「一緒に弾けたね!」という体験をさせてあげましょう。
- 憧れの曲を一緒に聴く: 「この曲、いつか二人で弾けたら素敵だね」と、目標となるような連弾曲を一緒に聴いてイメージを膨らませるのも良いでしょう。
5. ヤマハの先生との連携を密に
家庭での様子や下のお子さまの性格(お調子者で、褒められると伸びるタイプであること、今は少し自信を失いかけていることなど)を先生に具体的に伝え、レッスンの進め方や声かけについて相談してみましょう。先生からの的確なアドバイスや励ましは、お子さまの心に響きやすいものです。
6. 長期的な視点と、親御さんの心の余裕
「辞めたい」という波は、どんな習い事にもつきものです。特に、下のお子さまのようなタイプは、気分の浮き沈みが大きいこともあります。
- 焦らず、長い目で見守る: 今すぐに結果が出なくても、焦らないことが大切です。音楽との関わりは長く続くものです。
- 音楽を楽しむ気持ちが最優先: 技術の上達も大切ですが、それ以上に「音楽って楽しい!」という気持ちを育むことを第一に考えましょう。
- 親御さん自身が音楽を楽しむ: 親御さんが楽しそうに音楽に触れている姿は、何よりの動機づけになります。一緒に歌ったり、音楽に合わせて体を動かしたりする時間も大切にしてください。
おわりに
下のお子さまの「辞めたい」は、憧れと現実の狭間で揺れる成長の証であり、同時に「もっとできるはず!」という内なるエネルギーの裏返しかもしれません。その繊細なプライドと「褒められたい」「注目されたい」という気持ちを上手に満たしてあげることで、壁を乗り越える力を引き出すことができるはずです。
お兄さま(お姉さま)のコツコツとした努力、そして下のお子さまの持つ天性の明るさと表現力。それぞれの個性が合わされば、きっと素敵なハーモニーが生まれることでしょう。夢の連弾が実現する日を楽しみに、焦らず、お子さまたちのペースに寄り添いながら、音楽のある豊かな日々を育んでいってください。